
ビジネスの現場でよく耳にする「ブランディング」。なんとなく大切なことだと意識はしていても、いざ「ブランディングの意味は?」と聞かれると上手く答えられない方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、ブランディングの目的や種類、得られるメリットなどをわかりやすく解説。大伸社の経験をもとに、ブランディングの基礎を体系的に学べる内容にまとめています。ブランディングについて理解を深めたい方は、参考にしてみてください。
- 目次
ブランディングとは?
まずは、ブランディングについて詳しく見てみましょう。
- ブランディングの定義
- 顧客視点でのブランドのコア策定
- ブランディングの目的
- ブランディングの効果
それぞれわかりやすく解説していきます。
ブランディングの定義
「ブランディング」を日本語に訳すと「ブランド確立」「ブランド構築」といった意味になります。
ブランドとは、簡単にいえば「見聞きした瞬間、頭に浮かぶ独自のイメージ」のことです。ブランドを形成し、確立することは、「ブランディング=頭に浮かぶ独自のイメージを確立するための努力」といえます。
ブランディングは、BtoC企業や大手企業による、いわゆるテレビCMや新聞広告を打つようなことだけではありません。様々な行動を積み重ね、ターゲット顧客から企業のあるべきブランドイメージを連想してもらうことを目指す必要性があります。
顧客視点でのブランドのコア策定
顧客にブランドイメージを連想してもらうためには、顧客視点で「ブランドのコアを定めること」が必要です。ブランドのコアを定めることで一貫した取り組みを行えるようになり、確固たるブランドを確立できます。

ブランドのコアは3つのステップで策定をしていきます。
- 顧客が望み、競合ができずに、自社ができることを把握する
- 顧客も望み、従業員も理想とし、自社だからこそできる世界を描く
- 理想と現状の自社とのGAPを改善するためにできることを考える
ブランディングでは、上記に向けて活動をし続けることが大切です。理想や期待を裏切る行動をしないことにも注意を払わなければなりません。
1. 顧客が望み、競合が出来ずに、自社ができることを把握する

顧客が望み、競合が出来ずに、自社ができることとは、自社が保有する現状の武器を意味します。
まずはこの武器が何かを知ることが重要です。顧客経験や従業員の活動において、現状の顧客の期待と評価、自社のイメージ、競合のイメージを調査し、把握をしていきます。
2. 顧客も望み、従業員も理想とし、自社だからこそできる世界を描く

自社だからこそできる世界を描くには、2つのGAPを知る必要があります。まずは、顧客が理想とするブランドと現状の自社とのGAPを知ることです。
続いて、自分たちが理想とするブランドと現状の自社とのGAPを知ることが求められます。GAPを知ることができた後は、顧客の理想を踏まえながらも、自社が理想とするブランドの構築を検討していきます。
3. 理想と現状の自社とのGAPを改善するためにできることを考える

続いて、理想と現状の自社とのGAPを改善するために、何ができるかを考えます。
ここでは、半永久的に変わらない、本来目指したい姿をミッションやパーパスとし、そこに行きつくための5〜10年後の姿をビジョンとして描くことが重要です。
この結果、過去から大切にしてきたこと、今の自社の強みから、未来へのつながりをストーリー化することができます。 ブランドのコアを策定するにあたり、有効なフレームワークがMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)です。MVVは、企業の存在意義、目指すべき未来、そしてそれを実現するための行動指針を明確に示すものです。また、ブランドを伝えるためのツールとしても機能します。弊社の場合は、以下の内容を掲げています。
| MV | 大伸社コミュニケーションデザインの場合 |
|---|---|
| ミッション | 未来に挑戦する人と企業にデザインの力を |
| ビジョン | 共に考え 実践する 価値の共創パートナーへ |
| バリュー | 誠実 / リスペクト / 連携 / 感謝 / 挑戦 / 探求 / 情熱 |
詳しくは以下の記事をご覧ください。
関連記事:ミッション・ビジョン・バリューとは?事例から作り方までご紹介
ブランディングの目的
では実際にブランディングを行うにあたって、その目的はなんなのでしょう。
ブランディングを行おうと踏み出す理由には主に以下のようなものがあります。
- 事業の変革を促したい
- 事業の多角化が進み、自社らしさが曖昧になってしまった
- 他社との差別化要因を見出せず、事業が停滞しているので再興を図りたい
- メッセージやビジュアルがバラバラでコミュニケーションに一貫性がない
これらのパターンに共通するのは、「ビジネスの成功・成長をブランディングによって成し遂げたい」ということです。
ブランディングはあくまで手段であり、ビジネスの成功・成長のためにブランディングが貢献できることは何かを考えることが重要なのです。
ブランディングの効果

ブランドのコアをしっかりと定めた上でブランディングを行うと、上図のような好循環が回り始めます。
ブランドのコアが市場に受け入れられることで、ブランドに愛着を持つユーザー(ファン)が生まれ、顧客のエンゲージメントが向上します。
その結果、顧客満足度もアップすることで売上拡大や収益性向上を実現させることが可能です。これにより、社会的に自社の認知度と評判が向上している実感が得られるようになることで、従業員エンゲージメントの向上にもつながります。
さらに、従業員のモチベーションがアップすれば、スキルや生産性の向上だけでなく、商品やサービスの品質向上も期待できます。
このように、ブランディングを行うことで、自社のビジネスに好循環が生まれるのです。
ブランディングの分類
- コーポレートブランディング(企業ブランディング)
- パーパスブランディング
- 採用ブランディング
- 地域ブランディング
- オフィスブランディング
- BtoBブランディング
- 製品 / サービスブランディング
- サステナビリティブランディング
- グローバルブランディング
ブランディングには、発信する対象者として大きく2つに分かれます。アウターブランディングとインナーブランディングです。それぞれの解説をします。
アウターブランディング
アウターブランディングとは、社外に向けたブランディングのことを指します。企業の理念や価値を市場に伝え、顧客や取引先に「どのような企業か」を印象づけます。
例えば、広告、SNS、企業サイト、プレスリリースなどを通じて、ブランドの世界観や自社らしさを発信する取り組みを行います。単なる認知度向上ではなく、企業が大切にする価値観や強みを市場に浸透させることが重要です。
インナーブランディング
インナーブランディングとは、社内に向けたブランディングのことをいいます。社員一人ひとりが自社のMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)や会社の目指すべき方向性を理解し、自分ごととして体現できるようにすることが目的です。
ブランドの理念が社内で共有されていなければ、外部に対して一貫したメッセージを伝えることはできません。
ブランドを社内に伝えるツールには、社内共有のためのツールやブランドブック、クレドブック、社内報などの資料、ノベルティグッズなどがあります。
まずはインナーブランディングの地盤を固めてから、アウターブランディングに着手するという段取りが一般的です。
関連記事:インナーブランディングとは?
ブランディングの種類
以下では、代表的なブランディングの種類を紹介します。
- コーポレートブランディング(企業ブランディング)
- パーパスブランディング
- 採用ブランディング
- 地域ブランディング
- オフィスブランディング
- BtoBブランディング
- 製品 / サービスブランディング
- サステナビリティブランディング
- グローバルブランディング
コーポレートブランディング(企業ブランディング)
コーポレートブランディングとは、ブランド構築によって企業そのものの価値を高めるためのブランディングです。企業ブランディングともいいます。
単に企業のロゴやキャラクター、広告を作成することではありません。企業の本質的な価値を明確にし、それを社内外に一貫して伝えることで、顧客との長期的な信頼関係を築き、企業の持続的な成長を支えるための活動です。
ブランディングによって日々イメージを更新することで、企業イメージを良くし続ける取り組みのことを指します。
関連記事:コーポレートブランディングとは?手法や事例、効果を解説
パーパスブランディング
コーポレートブランディングを行う中で、自社が社会に存在する意義や理由、どのような価値を提供するかを見つめなおし検討し、定義し、世の中に発信することを軸にブランディングを行う戦略です。
「なぜその企業が社会に存在しているのか?」「どんな貢献を社会に行うのか?」といった視点から、企業の原点となる考えや根拠を表します。この活動により、社会において自社が存在する意義や与える影響を世間に認知してもらい、多くの共感や信頼を獲得することができます。
関連記事:パーパスブランディングとは?企業の存在意義を示すブランディング手法
採用ブランディング
採用ブランディングとは、転職者や新卒の方に、自社の魅力をより魅力的に分かりやすく伝えることでエントリーや内定辞退を防ぐ取組を行うことです。競合との差別化や自社ならではの強みが伝わらなければ採用に至らない為、まずは自社の魅力作りを先行して行い、まだ社会に出てない大学生に魅力的に伝えるにはどのような言葉やビジュアルであれば伝わりやすいか?を定義、発信することで、企業と価値観の合う人材を集めやすくなります。ブランドコアに共感した社員の定着率の向上が見込めます。
関連記事:求職者をファンにする」採用ブランディングの考え方とは
地域ブランディング
地域ブランディングとは、その地域が持つ独自の価値や魅力を明確にし、様々な角度から独自のアイデンティティを広く発信する取り組みです。地域色を出した特産品の開発やPR活動、地域の観光資源を活かしたイベントの実施などが挙げられます。
進学や就職で地方の人口が減少している課題から、地域を「ブランド」として広めていく必要性が高まっています。コロナ禍を経て都会からの移住者が増えている状況も、近年地域ブランディングへの注目が集まっている要因の一つです。
地域ブランディングは地域のイメージ向上や、経済活性化などを目的としています。
関連記事:自治体が目指す 地域ブランディングとは 事例から学ぶ効果的な戦略と進め方
オフィスブランディング
オフィスブランディングとは、オフィスを社員が働きやすく、かつブランドの価値を高められる場所にするためにリニューアルする取り組みです。社員のモチベーションの向上につながるだけでなく、来客の際に企業の理念を伝えることにもつながります。
BtoBブランディング
BtoBブランディングとは、BtoB(企業間取引)において自社のブランド価値を認知してもらい、顧客との信頼関係を構築するためのブランド戦略です。
BtoB企業では、対象顧客が絞られるため、一般的な認知度を上げるよりも、ターゲットに特化したブランディングが重要になります。それゆえ徹底した顧客視点に基づいた戦略が必要です。
顧客のニーズを満たす独自の強みを抽出し、信頼性や専門性を打ち出すことで、競合との差別化や競争力の強化を実現します。
関連記事:私たちが手がけるBtoBブランディングの考え方とステップ
製品 / サービスブランディング
製品 / サービスブランディングとは、特定の商品やサービスの価値を明確にし、競合との差別化を図るブランディングです。
製品・サービスの機能や品質、独自性、ブランドストーリーを訴求することで、消費者に選ばれやすくするための取り組みです。商品の魅力を視覚的に伝えるパッケージやロゴマーク、キャッチコピーも、製品 / サービスブランディングに含まれます。
サステナビリティブランディング
サステナビリティブランディングは、環境や社会に配慮した取り組みをブランドの核に据えたブランディング戦略です。CO2削減や森林保護など、「持続可能な社会を目指す」というサステナビリティの考え方に基づいた行動から、自社のブランド価値を高めます。
また、サステナビリティに関するレポートを作成することで、企業のコアをさらに発信し定着させることができます。
グローバルブランディング
グローバルブランディングとは、海外市場を視野に入れ、世界中の顧客に向けたブランディングを行う手法です。顧客視点に基づき、各国で一貫したブランドイメージを保ちつつ、多言語対応や文化に配慮した戦略が求められます。
海外市場における自社のブランドイメージを明確にするために、顧客と社内のブランドイメージを調査・把握し、ブランドのあるべき姿を定義する必要があります。
ブランディングで得られる企業側のメリット
ブランディングを行うことで得られる企業側のメリットは以下の通りです。
- 価格競争から脱しやすくなる
- マーケティングコストが下がる
- 社員のモチベーションが上がる
- 優秀な人材を集めやすくなる
価格競争から脱しやすくなる
自社ならではの強みを打ち出すことで、価格競争から脱しやすくなることが大きなメリットです。ブランドならではの価値を見出し、育てることは、他の競合商品・サービスとの違いが認知される、識別化につながります。
これにより、業界内で独自性のあるポジショニングを確立できるようになります。ユーザーに新しい選択肢を提示できれば、自然と価格競争から脱却できるでしょう。
マーケティングコストが下がる
マーケティングコストが下がることも、ブランディングを行うメリットです。
通常、新規顧客の獲得には広告宣伝費などの集客コストがかかります。しかし、ブランドが確立できていれば、Webマーケティング施策の一つである口コミの拡散やSNSでのシェアなどによる新規顧客の獲得が期待できます。
広告に費用を割く割合が少なくなり、集客コストを削減できるでしょう。
社員のモチベーションが上がる
ブランディングが成功すれば、自社ブランドへの誇りが生まれ、社員のモチベーションも上がりやすくなります。企業が大切にしている価値観や理念に共感して働く従業員が増えればエンゲージメント率が高まり、離職率が低減するだけでなく、日々の業務の品質も向上します。
優秀な人材を集めやすくなる
企業ブランドが確立されると、求職者にとって魅力的な企業として認識されやすくなります。働きがいや社風の透明性が高まることで、企業文化に共感した優秀な人材が集まりやすくなります。
ブランディングで得られる消費者側のメリット
企業がブランディングを行うことで、消費者側にもメリットがあります。ブランディングで得られる消費者側のメリットは以下の通りです。
- ストレスなく商品を選べるようになる
- 満足感を得やすくなる
- 商品選びの失敗を避けられる
ストレスなく商品を選べるようになる
商品やサービスのブランドイメージが確立していれば、消費者はストレスなく商品を選べるようになります。
現代社会はモノも情報も溢れかえっており、商品を探して選ぶことに疲れてしまう人も多いものです。明確なブランドイメージがあることで消費者が商品を選ぶ際の指針となり、商品の選択肢が絞られます。
満足感を得やすくなる
ブランドの価値が明確であるほど、消費者は「この商品を買ってよかった」と満足感を得やすくなります。そのプロセスで重要な役割を果たすのが、自己投影です。
自己投影とは、自己投影とは商品の購買や利用を通じて「自分はどんな人間か」を示すことです。PCならMacBook、車ならテスラなど、ブランドは持ち主そのものにも何らかの評価をもたらします。
顧客は特定のブランドを選定することで、自分自身のイメージを表現することができます。ブランドが提供する価値やメッセージ、ブランドの名前やロゴから連想されるイメージが、顧客の自己イメージと一致する場合、顧客はそのブランドに対して強い愛着を持ち、満足感を得やすくなるのです。
また、顧客がブランドの価値観や理念に共感することで、さらに自己投影が強化されます。これにより、顧客はブランドとの関係を深め、満足感を得ることにつながります。
商品選びの失敗を避けられる
ブランドが確立されていると、どのような価値が提供されるのかが事前にわかっているため、「思っていたものと違った」といった事態に陥ることなく、スムーズに商品を選べます。複数の商品や情報を比較し、調査する労力も不要です。
ブランディングのプロセス/手順

ここからは、ブランディングのプロセスと手順について解説します。ブランディングは、5つの手順で行います。
- プロジェクト設計
- 現状理解
- ブランドコアの定義
- 具体化と実行
- 効果検証と改善
1. プロジェクト設計
ブランディングを始める前に、まずプロジェクトの全体像を明確にします。ブランディングを行う目的や実施範囲を定め、チームの役割を定めます。
目的をはっきりと把握し、各工程での判断基準も明確となり、様々な優先順位もつけやすくなります。「ブランディングの活動を通じて何を果たしたいのか?」といった視点から、プロジェクトの設計を行いましょう。
2. 現状理解
次に、現場の分析を行います。ブランドを確立するために、「自社」「顧客」「社会」「競合」の4つの視点から分析を行います。
理想のブランドの姿として、「自社のありたい姿」と「顧客からの期待」が重なる部分がブランドコアの候補になります。その上で、競合が提供していない独自のポジショニングを取ることが理想です。以下のような外部環境分析・内部環境分析のフレームワークを取り入れながら、現状理解や把握に努めましょう。
- PEST分析/PESTLE分析
- 3C分析
- ファイブフォース分析
- クロスSWOT分析
3. ブランドコアの定義

現状調査をもとに、ブランドコアの設定を行います。ブランドコアを軸に一貫した取り組みを行うことで、確固たるブランドを確立できます。
企業としての志を定める「P-MVV」と、ユーザーにとっての価値を3つの視点で定める「ブランドベネフィット」を定めることで、ブランドコアを設定します。自社のブランドが何者で、何を目指し、どのような価値を提供するのかを明確にしましょう。また、これらの要素をメッセージとして第三者に説明できるよう、ストーリー立てしておくこともおすすめです。
4. 具体化と実行
ブランドコアが決まったら、具体的な施策に落とし込みます。
具体化と実行のフェーズにおいては、まずはインナーブランディングを進めて、社内に浸透した段階でアウターブランディングに進むという流れが理想的です。
社内に浸透しないうちに社外に対してブランディング活動を行っても、一貫性がなくなってしまい、顧客に混乱を与えてしまう可能性が高まるからです。統一されたブランドイメージを確立させ、社内外に届けることで、ブランドへの信頼と愛着を深めることができます。
インナーブランディングでは、ブランドベネフィットなどのブランドメッセージを落とし込んだクリエイティブであるブランドブックやムービー、クレドブック、社史、社歌の制作、社内向けノベルティの作成、社内イベントの開催などがあります。
アウターブランディングは、まず顧客視点によるブランドターゲットやペルソナの設定、カスタマージャーニーの策定をすることが肝心です。ブランドを想起させるトリガーとなるブランドロゴの作成から、WebサイトやSNSでの発信、メディア広告の運用、イベントの開催、展示会への出店、店舗空間の変更まで多岐に渡ります。
関連記事:ブランディングでも重要なペルソナ設定。その解像度を上げるポイントとは?
関連記事:カスタマージャーニーの作り方
5. 効果検証と改善
ブランディングに取り組み始めてから一定期間が経過したら、効果の測定も行いましょう。ユーザーリサーチなどで得た数値をもとに定点で観測を実施し、どのような取り組みが評価されているのか見直すことが大切です。
ブランディングは時間を要します。継続的に行う必要があり、市場や顧客の変化に合わせて戦略やペルソナ像を定期的に見直したり、効果測定と改善を繰り返したりすることも必要です。
なお、ブランディングの詳しい手順については、以下の記事も参考にしてみてください。
関連記事:ブランディングの方法・手順とは?
【課題別】ブランディング戦略のやり方
ここからは、企業が抱える課題別にブランディング戦略のやり方を紹介します。
- 初めてブランディングを行う企業
- ブランドの定義はされているが、社内浸透ができていない企業
- 社外へ適切に伝える内容/手段が決まっていない企業
初めてブランディングを行う企業
初めてブランディングを行う企業の場合、【フェーズ1】プロジェクト設計、【フェーズ2】現状理解、【フェーズ3】ブランドコアの定義、【フェーズ4】具体化と実行、【フェーズ5】効果検証と改善という5つのプロセスに沿ってブランディングを進めましょう。その後【フェーズ4】と【フェーズ5】を繰り返す必要があります。
ブランドのコアが明確でなく、ブランドとしてのビジョンや志が見える化されていないのであれば、【フェーズ1】からの取り組みが必要です。
関連記事:ブランディング戦略とは
ブランドの定義はされているが、社内浸透ができていない企業
ブランドが定義されている場合、必ずしも全ての手順を踏む必要はありません。「ブランドの定義はされているが、社内浸透ができていない企業」の場合、フェーズ4の具体化と実行から始めてみるとよいでしょう。
特に、インナーブランディングの見直しに注力することが重要です。
社外へ適切に伝える内容/手段が決まっていない企業
社外へ適切に伝えるための内容や手段が決まっていない場合も、具体化と実行のフェーズから取り組みましょう。インナーブランディングが問題なく済んでいる場合は、アウターブランディングが重要となります。
事例で見るブランディング
ここからは、実際にどのようなブランディング事例があるのかをご紹介します。
- 「企業」ブランディングの成功事例
- 「事業」ブランディングの成功事例
- 「サステナブル」ブランディングの成功事例
- 「地域」ブランディングの成功事例
「企業」ブランディングの成功事例
企業ブランディングに成功したスターバックスの事例です。「The Third Place」(自宅でも職場でもない、「第三の場所」)というブランドコアを定め、プロダクトやサービス、店舗空間、社員教育を徹底しました。一貫性のある「おもてなし」を実施することで、顧客にとって真に安らぐ場所を提供し、世界90ヵ国以上に展開する一大グローバルチェーンに成長しました。
しかし、スターバックスでは、2007年から2008年にかけて安定的に売上高は増えたのに利益が半減したことがあったといいます。原因は教育が不十分なバリスタが店頭に立っていたり、売り上げ向上のためにコーヒー以外の商品が多く販売されていたりしたことで「何の店かわからなくなってしまった」ことです。これにより、既存店での売上高の伸び率がマイナスになってしまいました。
この窮地を救うべくCEOに復帰した創業者のハワード・シュルツ氏は、経営合理化に利益率の向上策を採るだけでなく、「原点回帰」を実施しました。多少の無駄があっても、「スタバらしさ」を取り戻そうと決意したといいます。シュルツ氏は、リスクを負いながらもバリスタの再研修や新しいコーヒーの商品開発を行い、スターバックスらしさ=「The Third Place」を取り戻すことができました。そして今もなお成長を続けています。
「事業」ブランディングの成功事例
弊社でも数多くのブランディングを手がけているなかで、株式会社NTTドコモ様(以下、NTTドコモ)のOpen RANサービスブランド「OREX®」の事例をご紹介します。
「OREX®」は海外向け新事業であり、こちらのサービスブランディングをご支援しました。
サービスブランディングを実施する前は、海外向け新事業のサービス内容が分かりづらく、潜在顧客へのブランド浸透や社内での共通認識醸成に課題がありました。そこで弊社では、社内メンバーを巻き込んだワークショップを通じてブランド構築を提案・実施し、ネーミング、ロゴ、スローガン、ビジョン、世界観を策定しました。また、海外展示会でのブランド披露目を支援し、PRチームとして通年でサポート、事業本格化に伴う新会社設立も支援しております。
上記のような活動を通じて、社内メンバーの共通認識が醸成されたと共に、お披露目活動によって国内外でのメディア露出が増加し、サービス認知度が向上しております。
「サステナブル」ブランディングの成功事例
サステナブルブランディングでは、株式会社丸運様の事例をご紹介します。
株式会社丸運様は、2021年度からESG経営へと移行する中で、より長期的に社会課題に取り組む方向へと舵を切り、レポートの発行によりブランドイメージの向上やSDGsの意義づけ、社内外への認知を広めていきたいとご相談いただきました。
初のレポート発刊ということで、提案前にレポートの特性や必要性、トレンドについてのレクチャーを実施。理解を深めていただいた上でご要望をヒアリングしました。最終的には、「ESGへの取り組み・実績を軸に、最適な物流ソリューションを提供する丸運のポテンシャル・企業価値をステークホルダーに知っていただくレポートを目指す」ことに決定。
結果、初めてのレポートということで注目度も高く、二年目のサステナビリティレポートの制作も行うこととなりました。
アウターブランディングの中の一つの取り組みとしてサステナビリティレポートを作成し、企業のブランドコアをさらに発信・定着できた事例です。
「地域」ブランディングの成功事例
「地域」ブランディングでご紹介するのは、「島×生活×アート」のキーワードでブランディングに成功した、瀬戸内海の「直島」の事例です。
瀬戸内国際芸術祭はもちろん地域ブランディング成功の要因といえますが、それに加え、直島は「体験価値によるブランド化」が行えているというのが大きな特徴です。
現代では「モノ」だけでなく「コト」に価値を見出すという経済の流れがあり、単なる商品価値ではなく「体験価値」が重視されています。そんな中、直島には海を渡って島を歩く中での感動体験や、島民と多様な形で交流する中での交流体験など、直島でしか感じることのできない価値があります。
ブランディングとマーケティングの関係性
最後に、よく混同されがちなマーケティングとブランディングの関係についてご説明します。
ブランディングが、「頭に浮かぶ独自のイメージを確立するための努力」である一方、マーケティングは「ブランドの価値を自分たちで伝える取り組み」であるといえます。
「共創」や「パーパス」がブランドの重要な要素となるに従い、現在ではブランディングをマーケティングよりもさらに経営に近いものとする見方が優勢となっています。この考えに基づくと、戦略及び戦術の階層は下の図のようになります。

ブランドとは「ユーザーの頭の中に浮かぶ魅力的な独自のイメージであり、他社に真似されにくい、その企業のビジネス資産」という定義を受け入れるならば、マーケティング戦略が変わることでブランドが変わる可能性はありません。また、「独自のイメージであるビジネス資産」としてのブランドを変更できるのは、経営戦略の大きな変更しかありません。
以上から、現代においてはブランディングとマーケティングは別物で、ブランド戦略はマーケティング戦略より優位に位置付けられるものと考えるのが良いでしょう。
ブランディングで事業を成功・成長させるために
本記事では、「ブランディングとは何か」という基本的な認識から事例や戦略、活用方法など詳しい部分まで幅広く解説しました。
ブランディングでは目的設定や現状分析、ブランドコアの定義など、いかに基礎を組み立てられるかが重要です。しかし、ブランディングを成功させることは簡単ではありません。的確なブランディング戦略や戦術を組み立てるには、プロのアドバイスを受けながら進めることがおすすめです。
ブランディングにご興味をお持ちなら、株式会社大伸社コミュニケーションデザインにご相談ください。
弊社では、ブランド策定・インナーブランディング、アウターブランディングの3つの領域から企業・プロダクトのブランディング支援を行っている企業です。
ブランディングからマーケティング戦略、デジタルコンテンツ、クリエイティブ制作まで、お客様のニーズに最適なソリューションを幅広く提供しています。VR/AR/MRなどの新しい技術も積極的に取り入れています。
ブランド策定やブランド浸透・育成のための社外、社内のコミュニケーション戦略の立案から実行まで、お客様との密接なコミュニケーションを重視し、伴走しながら支援いたします。
今なら、ビジネス成長を加速させる「実践型コーポレートブランディングガイド」を、無料でDLしていただけます。ぜひ、以下よりご利用ください。
【無料ダウンロード】ビジネス成長を加速させる 実践型コーポレートブランディング はこちら
【参考文献】
『手にとるようにわかる ブランディング入門』(金子大貴著、 一色俊慶著)
Heskett, Sasser & Schlesinger (1997) The Service Profit Chain
DCD事例紹介 極東産機株式会社様/オンライン葬儀サービス『ichi-e(いちえ)』のブランディング
https://www.daishinsha-cd.jp/work2/ichi-e/
2015 年度事例研究現代行政Ⅰ最終レポート『直島における地域活性化の事例研究」
https://www.pp.u-tokyo.ac.jp/graspp-old/courses/2015/documents/graspp2015-5140040-5.pdf
innova 「成功事例・失敗事例から見るブランド戦略の効果」
https://innova-jp.com/branding-strategy/

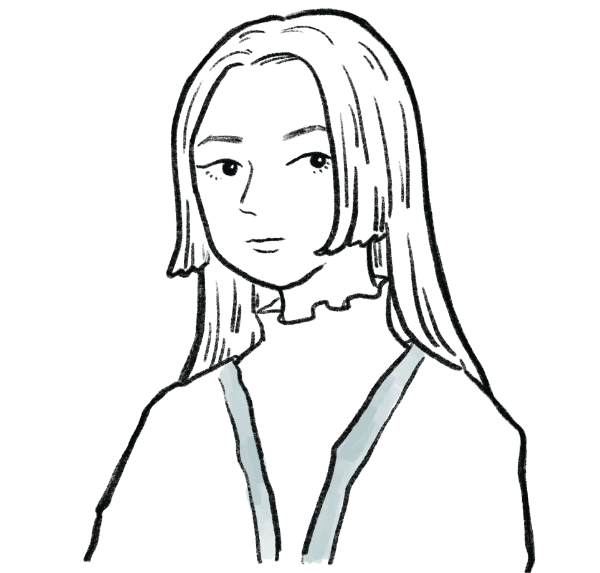

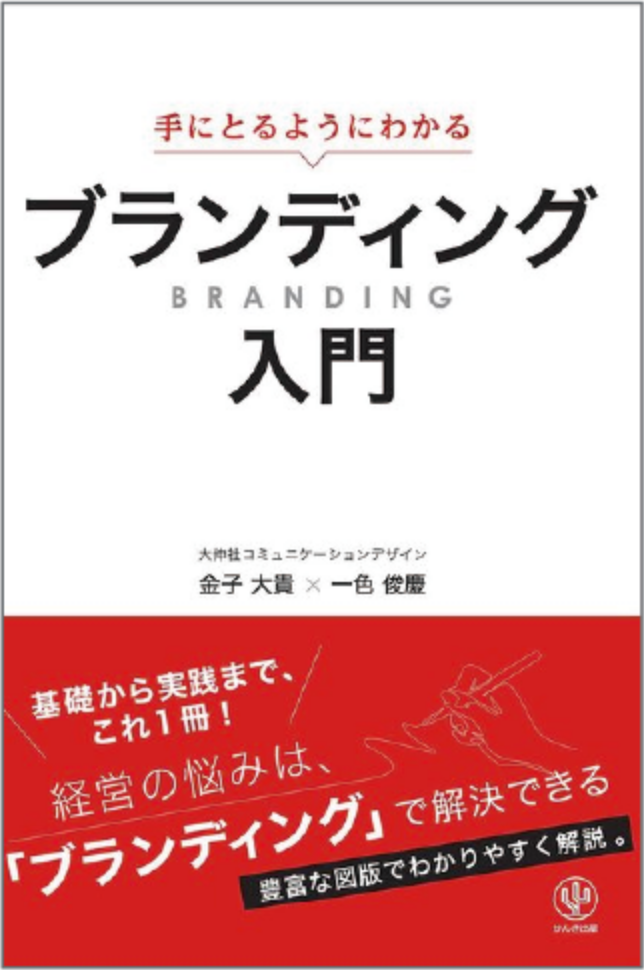 株式会社 大伸社コミュニケーションデザイン チーフ ブランディングディレクター コピーライターとして、広告・宣伝のクリエイティブ開発の経験を経て、ブランディングに特化したプランニング・コンサルティングを担う現職へ。大手上場企業から中小企業まで、企業のリブランディングプロジェクト、新製品のコンセプト開発、ブランド浸透戦略立案などの幅広い業種業態でのブランディング支援を実施。
株式会社 大伸社コミュニケーションデザイン チーフ ブランディングディレクター コピーライターとして、広告・宣伝のクリエイティブ開発の経験を経て、ブランディングに特化したプランニング・コンサルティングを担う現職へ。大手上場企業から中小企業まで、企業のリブランディングプロジェクト、新製品のコンセプト開発、ブランド浸透戦略立案などの幅広い業種業態でのブランディング支援を実施。

