
第8回の今回の記事では、ブランディングを実施するにあたって始めに行う、企画書の作成について解説します。どのような企画書を作成すればいいのかわからない、という方はぜひこれを参考に、手を動かしてみてください。
- 目次
ブランディングプロジェクト立ち上げに向けた企画書/提案書の重要性
「自社もブランディングに着手しよう」と決意をしたら、会社から承諾を得るためにまず企画書/提案書を作成する必要があります。特にブランディング活動は、社内の人間を多く巻き込むことになるため、ブランディングに関わるメンバーの認識や目指すべきゴールを揃える必要があります。そのため、実施目的や戦略、メリットや、失敗しないためのポイントを共有することで、全員が同じゴールを目指して走り出すことができます。
では実際に企画書/提案書を作成するときに必要なことは何でしょうか。それはストーリーです。先ほど挙げた内容を、しっかりと順序立てて説明し、ブランディングの必要性を理解してもらえるような企画書でなくてはなりません。
しかし実際に作成しようとしても、何からまとめ始めればいいのかがわからない方も多いのではないでしょうか。そんな方のために、ここからは資料を作成する際の具体的な項目をご説明します。
ブランディングプロジェクトの立ち上げに向けた企画書の項目
実際にブランディングプロジェクトを立ち上げても良いのか、上長や役員から承認をもらうための企画書作りに必要な項目とどのような内容が必要になるのかを解説していきます。
①会社ならではの条件や課題を整理し、訴求ポイントを掴む
まず初めに、自社が抱えている課題を整理します。例を出すとすれば、
・製品の差別化が難しくなってきた
・会社の認知度が低く、新規採用に苦戦している
・SDGs、サステナビリティやDX戦略など大きな方針を決める軸がなく、自社らしさが出せていない
などがあります。このような課題に対して、ブランディングを行うことで解決につながるものを優先順位をつけた上でピックアップします。
②ブランディングによる効果を説明し、課題解決への道筋を提示する
次にこれらの課題に対して、ブランディングを行うことでどのような効果があるのかを説明します。先ほどの例にならって考えると以下が一例として挙げられます。
・製品の差別化が難しくなってきた
→ブランドを確立することで新規参入時の効率的な認知向上をはかり、顧客を獲得できる。
・会社の認知度が低く、新規採用に苦戦している
→ブランドを確立することで、競合企業との差別化となり、認知がアップ。理念に共感し入社希望者が増え、また入社後の定着率も向上する。
・SDGs、サステナビリティやDX戦略など大きな方針を決める軸がなく、自社らしさが出せていない
→ブランドを確立することでSDGsやサステナビリティで果たすべき方向性が定まり、ブランディング活動を戦略的に推進していくことでブランド力が向上。成長への期待から長期的な株保有者率の向上が見込まれる。
このように、ブランディングを行うことによってさまざまな自社の課題の解決につながることを明確にさせます。
③ブランディングの効果・メリットなどの事例を紹介し、興味付けを行う
実際にブランドの効果を大きく感じる場面の事例を交えながら話すことでより理解してもらうことで企画書/提案書の説得力が増します。
例えば、スターバックスのロゴマークのあるコップに入ったコーヒーと、ただの白いコップに入ったコーヒーがあったとします。この2つは同じ材料、同じ品質だとした時、あなたはどちらに魅力を感じ、より高いお金を払いたいと感じるでしょうか。多くの人はスターバックスのロゴマークが入ったものを選びます。スターバックスのロゴマークがあることで、安心感・信頼感・味の美味しさ・洗練さを勝手に感じ取っているからです。つまり反対に考えると、たとえどれだけ良い製品を開発したとしても、ブランドの影響力で負けてしまうと、買ってもらえる機会を逃してしまうのです。
このように日常生活でもイメージしやすい事例をあげることで、よりブランドに対する理解を深めることができます。
④ブランディングの必要性を訴え、やる気にさせる
製品の良さ=その製品を選ぶ理由、にはならないということを④でご説明しました。しかし、世の中では、素晴らしい製品を作り提供していくだけでも、ビジネスの成長は可能です。では一体なんのためにブランディングを行うのかを、次に説明する必要があります。その理由は、製品・サービスの機能的な魅力だけではなく、評判/イメージ作りによる情緒的な魅力を作ることでビジネス成功の可能性を高めるためです。
このように、ビジネス(事業戦略)とイメージ・評判(ブランド)の両輪を回す活動が、会社のビジネスを成長させる鍵となるのです。
⑤競合他社の取り組みを紹介し、やらなきゃまずい!という状態を醸成する
ここまで、自社の課題に対してブランディングを行うことでどのような解決が得られるのか、そもそもブランド、ブランディングとはなにかを説明してきました。十分にブランディングの必要性が明らかになったら、次は自社の競合他社に当たる会社ではどのようなブランディングを行っているのかを調査し、共有することが必要です。
同業の競合他社だけでなく、他業界のベンチマークなどからもヒントを得られる場合があります。また、グローバルな視点で海外の同業他社を調べることで、新たな気付きや発見があるかもしれません。広い視野を持って競合他社を探し、調査することが重要となります。
⑥ブランディング全体のプロセスを伝え、プロジェクトのイメージ付けを行う
ブランディングの大きな流れは以下のようになります。

現状理解にあたって必要なリサーチや、コアを定義するにあたってのワークショップなどにも多くの時間を要する他、実際のアウトプットをどのようなものにするのかによってもかかる時間は変わってきます。また、ブランディングを行なっていく手順の中で自社の課題がどこにあるのか?どのフェーズに比重をかけるのか?を検討しながら作成するのがいいのではないでしょうか。
⑦今後のブランディングに関する制作物についてイメージ付けを行う
⑦のプロセスと合わせて、どのようなアウトプットを行うのかという説明も必要です。以下の画像はインナー/アウターブランディングのツールの例となります。

このように、成果物にはさまざまな種類があります。この中から、ブランドコアを軸にそれぞれどのようなことを実現したいかに合わせてアウトプットを何するか考える必要があります。
例えばインナーブランディングの一番初めのステップとして、社内への認知・浸透を目的としたアウトプットを考えるのであれば、一人の人間ではなく全ての従業員に平等に伝わるような「ブランド発表会」が考えられます。他にも、定めたブランドコアをより深く知る、ブランドブック、ブランドムービー、クレドブックの配布などが考えられます。
⑧ ブランディング実施後の検証と改善の必要性
取り組む内容についての最後の説明として、ブランディング活動を行った後の効果検証と改善を行う必要性を説明することが重要です。
ブランドは放っておけば、どんどん劣化していきます。ブランドらしい取り組みに外れていないか、常にチェックすることが必要です。そのため、このブランディングプロジェクトには終わりはなく、実施した後も常に改善を重ね、独自のブランドを確立し続けることが重要であることをしっかりと説明しておきましょう。
⑨スケジュールと体制
最後に、プロジェクトのスケジュールと体制を明確にしておきましょう。
ブランディングプロジェクトの期間については、会社の現状レベルや体制(参加できる人数や専任度合い)によって違ってきます。弊社の支援実績からおおよその目安を言いますと、①プロジェクト設計~現状理解に3 カ月、③ブランドコアの定義に3 カ月、④具体化と実行への準備に2 ~ 3 カ月かかります。そうなると早い会社では6 カ月、遅い会社だと9 カ月でブランディング・プロジェクトが完了し、その半年後以降に効果検証を行い、プロジェクトの評価ができ、継続的なブランディングの運用に入っていくことになります。
体制に関しては、まず初めに最上位に責任者として、ブランド・オーナーが入ります。実際にプロジェクトを牽引するプロジェクト・マネージャーは、実行に責任を持つ人物が適任です。関係各所に顔が利き、調整能力と推進力のあるミドルマネージャークラスが担うケースが多くなります。

まとめ
今回の記事ではブランディングの企画書作成について詳しくご説明しました。
ブランディングは長い時間をかけて社内外の多くの人間を巻き込む、大きなプロジェクトとなります。そのため上長の承認を得るにはブランディングが自社に必要である理由についてしっかりと理解をしてもらうことが必要です。
この記事が、より良いブランドとなるための一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【参考文献】
『手にとるようにわかる ブランディング入門』(金子大貴著、 一色俊慶著)

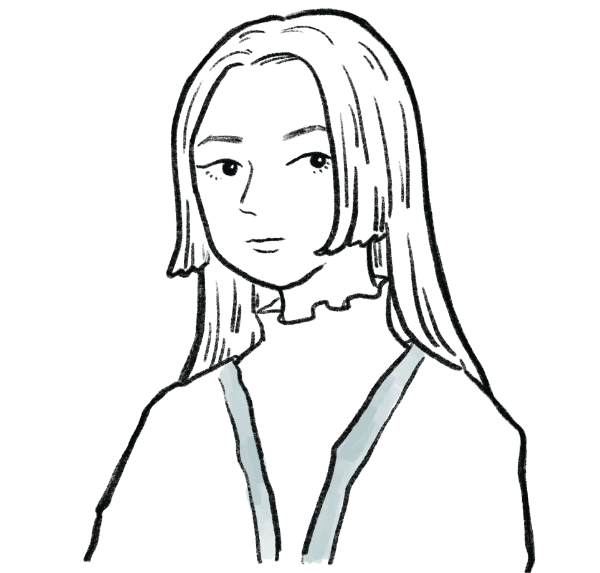

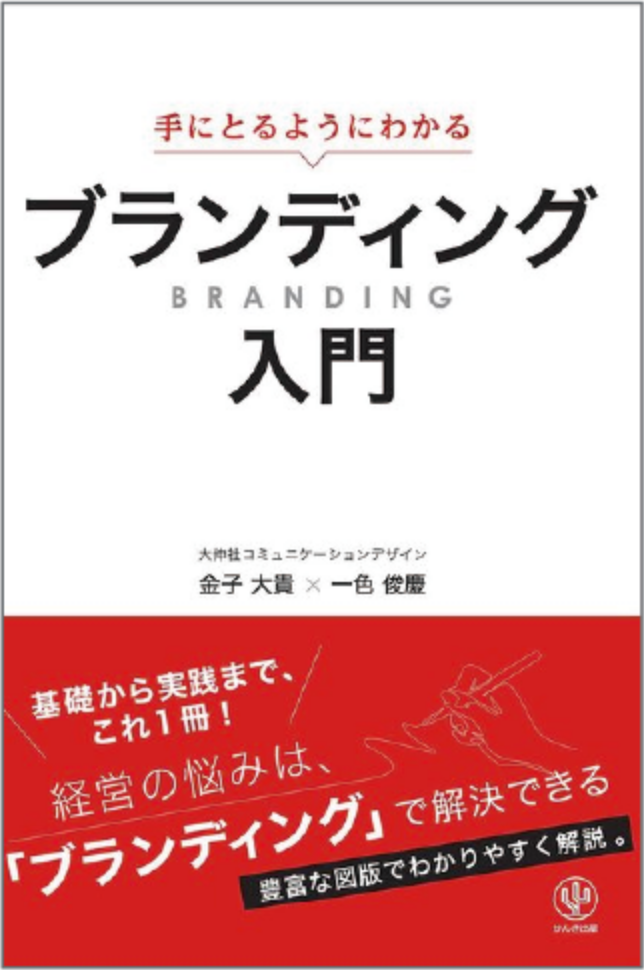 株式会社 大伸社コミュニケーションデザイン チーフ ブランディングディレクター コピーライターとして、広告・宣伝のクリエイティブ開発の経験を経て、ブランディングに特化したプランニング・コンサルティングを担う現職へ。大手上場企業から中小企業まで、企業のリブランディングプロジェクト、新製品のコンセプト開発、ブランド浸透戦略立案などの幅広い業種業態でのブランディング支援を実施。
株式会社 大伸社コミュニケーションデザイン チーフ ブランディングディレクター コピーライターとして、広告・宣伝のクリエイティブ開発の経験を経て、ブランディングに特化したプランニング・コンサルティングを担う現職へ。大手上場企業から中小企業まで、企業のリブランディングプロジェクト、新製品のコンセプト開発、ブランド浸透戦略立案などの幅広い業種業態でのブランディング支援を実施。

